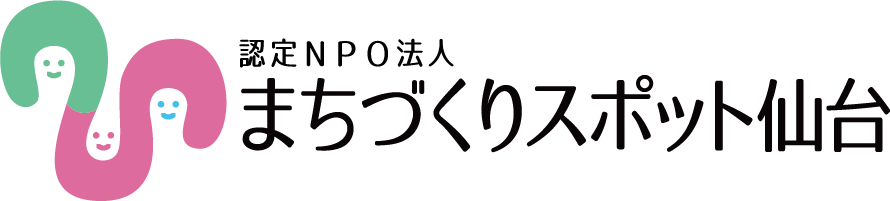- まちスポ仙台を知る
まちスポ仙台を知る
ABOUT
- まちスポ仙台とは(about/index.html)
まちスポ仙台とは
まちスポ仙台のビジョンやスタッフ紹介をご覧いただけます。
-
団体概要
理事紹介、情報公開、アクセスなどの基本情報を掲載しています。
- まちスポ仙台とは(about/index.html)
- 活動を知る
活動を知る
ACTION
- 活動紹介(activities/index.html)
活動紹介
まちスポ仙台は「ひろげる」「うみだす」「そだてる」の3つを軸に活動しています。
-
ひろげる
既に想いをもって活動を進めている方同士をつなげて、更なる活動の広がりをつくります。
-
うみだす
地域課題を新たな仕組みを生み出すことで抜本的・持続的な課題解決を目指します。
-
そだてる
若い世代のまちへの関心・興味をはぐくみ、次世代のまちづくりを担う人材育成を行います。
- 活動紹介(activities/index.html)
- 交流スペースを利用する
- まちスポ仙台を知る
- 活動を知る
活動を知る
ACTION
- 活動紹介(activities/index.html)
活動紹介
まちスポ仙台は「ひろげる」「うみだす」「そだてる」の3つを軸に活動しています。
-
ひろげる
既に想いをもって活動を進めている方同士をつなげて、更なる活動の広がりをつくります。
-
うみだす
地域課題を新たな仕組みを生み出すことで抜本的・持続的な課題解決を目指します。
-
そだてる
若い世代のまちへの関心・興味をはぐくみ、次世代のまちづくりを担う人材育成を行います。
- 活動紹介(activities/index.html)
- 交流スペースを利用する
つながるみつける日記 ・episode11・
つながるみつける日記とは
みなさんこんにちは!
まちづくりスポット仙台でインターン生として活動している嶺岸ほのか(みねぎしほのか)です。このブログでは、まちづくりスポットで活動されている団体さんの想いやお困りごとなどを私なりの視点から発信し、団体さん同士がつながるきっかけとなることを目標としています。
最近は、「ブランチオーガニックマーケット」に出店されている方を中心に、インタビューをさせていただいています!
「人と人のつながり」を大切にしながら、私自身も学び、成長する日々です。このブログを通じて、新しい発見や繋がりが生まれるきっかけになれば嬉しいなあと思います。
ぜひぜひ、この記事を読んだら、気軽に反応もらえると嬉しいです!
▶︎#学びをシェア
ブランチオーガニックマーケットに出店されている、一般財団法人 日本熊森協会宮城県支部(愛称:みやぎ・なめとこ山の会)小松さんにインタビューを行いました!

「クマも棲める森を。未来世代へ」−−みやぎ・なめとこ山の会が伝えたいこと
ブランチオーガニックマーケットに出店されていた「一般財団法人 日本熊森協会 宮城県支部」のブースで、支部長の小松さんにお話を伺った。
「熊森協会」と聞いて、「クマを守る活動をしているのかな」と思った方が多いと思う。私もその一人だった。しかし、小松さんは穏やかな笑顔でこう答えた。
「クマをはじめとする野生生物が命の循環を全うできる豊かな水源の森を今はまだ存在しない未来世代に少しでも多く残す活動をしています」
その言葉の意味を深く知るにつれ、この活動が私たちの暮らしと未来に深く関わっていることが見えてきた。
65歳で、会社員として働きながら支部長を務める
小松さんは1960年生まれの65歳。「見えないですね」と驚くと、「ありがとうございます」と笑った。
現在は嘱託(しょくたく)の会社員として働きながら、熊森協会宮城県支部の支部長を務めている。
タバコも吸わず、最近は飲みにも行かない。「仙台で一晩飲んだら、一年分ぐらいの活動費が飛んでしまいますから」。その分を活動費に充てているという。
日本熊森協会宮城県支部、愛称「みやぎ・なめとこ山の会」。現在の会員数は約70名で、全国に約2万人いる熊森協会の中では小規模な支部だ。
しかしその活動には、この土地ならではの深い思いが込められている。
宮沢賢治の物語と先住民族の言葉が重なる
「なめとこ山」という名前は、宮沢賢治の『なめとこ山の熊』に由来する。物語の中で、月夜に母子の熊が遠くの山を見ながら「あれは残雪なのか、白い花が咲いているのか」と語り合うシーンがある。それを後ろから聞いていた猟師の小十郎は、熊の言葉がわかるほど熊のことを知り尽くしていた。結局その夜、小十郎はそのまま、こっそり こっそり帰っていく——人と熊の共生を描いた、心に残る場面である。
この物語の一場面が、会のロゴマークになっている。デザインしたのは、富谷市のピザ屋「ウッディンシップ」の店長で、宮城県支部立ち上げメンバーの一人。木工やチョークアートが得意で、店もほとんど自作という才能豊かな人物だ。宮城県支部の副支部長も務めている。
そしてこちらにも驚いた。「なめとこ」という言葉には別の意味もある。愛称を付けた後に調べてみると、日本の先住民族である蝦夷(えみし)の言葉で「冷たい水が湧くところ」という意味があったという。宮城県図書館の3階には、小学校教師の方が趣味で作ったアイヌ地名に関する分厚い資料があり、そこに記されていた。利府町の「利府」も、蝦夷の言葉で「丘が多いところ」という意味があるそうだ。
森と水、そして命の循環——偶然にも、名前そのものが活動の本質を表していた。

クマはシンボル、本当に守りたいのは森全体
「クマはアンブレラ種なんです」と小松さんは説明する。体が大きく、さまざまなものを食べるクマが生きられる森には、タヌキやキツネ、昆虫や様々な植物、そして目に見えないたくさんの微生物たちも暮している。クマという大きな傘の下で、生態系全体が循環しているのだ。
「クマって、植物を中心にいろんな食べ物を食べるんです。クマがいるということは、その森はクマを養うだけの食べ物があるということ。そうしたら他の動物たちも食べるものがある、植物がよく育つ土を作るミミズや微生物もたくさんいるっていう場所になるんですね」
日本熊森協会宮城県支部の目標は、「クマをはじめとする野生生物が命の循環を全うできる豊かな水源の森を、今はまだ存在しない未来世代に、少しでも多く遺す活動をすること」。私たちは土を作ることができない。土壌学者の藤井一至さんによれば、地球ができて約46億年、そのうち約5億年前に微生物や昆虫、植物、動物たちの営みで土というものができたという。それまでは岩石や粘土ばかりだったのだ。自然資本なくして、経済も暮らしも成り立たない。そんな当たり前のことを、改めて見つめ直す活動なのだ。
きっかけは「3.5%の人が動けば変わる」という言葉
小松さんが活動を始めたのは約4年前。きっかけは、経済学者の斎藤幸平さんがラジオで話していた言葉だった。「自然環境を守らなければ、人類は生きていけない」——なぜ経済学者がそんなことを言うのか。疑問に思って著書『人新世の「資本論」』を読んでみたという。
そこには、「まず3.5%の人が今この瞬間から動き出すのが鍵である」という言葉があった。
「その3.5%の人になろうと思って、熊森協会の本部にメールを送ったんです」
結果、宮城県支部を立ち上げることに。それまで宮城県には会員はいたが、支部はなかった。富谷市のピザ屋の店長とブランチ仙台オーガニックマーケットを紹介してくれたもう一人の方と共に立ち上げ、現在に至る。立ち上げの際には、そのピザ屋で会議をしたり、まちづくりスポットのイベントに出店したりと、少しずつ活動を広げてきた。
現在は年会費1,000円から参加できる応援会員を募集している。日本熊森協会は会費と寄付だけで運営し、どの政党にも属さない独立した活動を続けている。1,000円の会員でも、年に2回発行される会報誌が届き、活動の様子を知ることができる。「別に金額の問題じゃないんです。関心を持っていただけることが大切」と小松さんは語る。
開発が進む富谷で、クマは今
富谷市に住む小松さんは、近年の開発の速さに危機感を抱いている。今まで山だった場所が切り崩され、宅地や道路になっていく。
クマたちは母から子へ、約1年半をかけて季節ごとの食べ物とその場所を教えながら移動する。木登りや、木の実の採り方も教える。お母さんに教えられた以外の場所にはあまり行かないクマもいれば、お腹が空きすぎて自分で新しい場所を開拓するクマもいる。しかし、教えられた場所を自分の子供に教えようとしたとき、そこは去年とは全く違う景色になっている。
「クマにとっては、びっくりですよね。あっという間に変わっちゃいますから」
高速道路のフェンスを乗り越えて道路を横断するクマ。富谷の北側あたりの高速道路には「熊に注意」の看板が出ている。「今までここ通っていたのだから通れる」とクマは思っている。そこに車が来る——事故が起きるのは当然なのかもしれない。
「Googleで今の富谷の様子を見ると、よくここにクマが来ているなって思います。本当に人が切り崩したところばっかりしかなくなっちゃっているので」
報道のあり方にも疑問
最近の栗原市でのクマのニュースについて尋ねると、小松さんは複雑な表情を見せた。
「亡くなった方がいると、もうここぞとばかりに特集になっちゃう。クマは悪者になっちゃうんです。でも本来は自然界にいなければいけない動物なんです。その自然界がどうにかなっちゃったから、人のいるところまで来てしまう」
マスコミは視聴率のために、日本中で起きたクマの目撃情報を全国版で報道する。しかし、トンボなどの昆虫が激減していることは報道されない。自然環境の変化、気候変動、水路がコンクリートで固められてヤゴが住めなくなっていること——そういった根本的な問題は、なかなかニュースにならない。
「クマが目立つからニュースになるけど、そういう報道って印象操作、情報操作みたいな感じですよね」
まちづくりスポットにも「虫博士」として知られる向井先生さんが夏場によく来られています。小松さんが昆虫の話を聞いたところ、「いつもは採れていた虫もなかなか採れなくなったな」と言っていたそうだ。

「どう生きるか」を問いかけたい
「一番伝えたいのは、私たちの生活はどうなんだっていうこと」と小松さんは語る。
野生生物はゴミを出さない、無駄なことをしない。一方で私たちは、大量の自然資源を使って食べ物を作り、余ったら捨てる。買ったものも使えるものがあってもゴミとして出す。便利さを享受しながら、野生生物に対して無関心だったり、蔑んだ目で見たりしていないだろうか。
「ブランチ仙台周辺の丘陵地帯は元々、野生生物の居場所だったんですよね。それを奪っておいて、クマは目撃されただけで捕殺されてしまう。人命は大切ですから難しいですよね。人間はこれからも増えていって、どうしても住むためには山を切り崩さなければならないってなっちゃう」
ジブリ映画1994年7月公開『平成狸合戦ぽんぽこ』や1997年7月公開の『もののけ姫』を思い出す。
「どうしてったらいいのでしょうね。でも、そこを今生きている人たちが考えなきゃいけない。先送りしたら、未来世代の方にどうなるのって。『何を考えていたんだ、昔の人』みたいになっちゃいますもんね」
だからこそ、少しずつでもいい。森に広葉樹の種を蒔いて育てたり、こういう情報を伝えたり、「水源の森の木を伐って風力発電風車を山の中に建てるのはどうなのか」と声を上げたり。小さな活動だけれど、積み重ねていくことが大切だ。
「シジュウカラガンを復活させた人たちも、『99.9%不可能』って言われていたらしいです。でもやるって決めてやっていたら、どんどん協力者が現れてきて、今は1万羽以上のシジュウカラガンが宮城県北部の伊豆沼周辺で越冬するまでに回復してきた」
仙台ではかつて、ガンを10羽捕ったら7羽ぐらいがシジュウカラガンだったというほど、シジュウカラガンが多くいた。それを保護し、復活させた人たちがいる。その活動を学びながら、みやぎ・なめとこ山の会も「できること」を続けていく。
これからも、小さな一歩を積み重ねて
インタビューの最後、小松さんに好きな食べ物を尋ねると、「カレーライスですね」と笑顔で答えた。昔から好きです。ネパールに行った時に初めて飲で覚えたミルクティー(チャイ)も好きだという。「甘いから」と素直に理由を話す姿が印象的だった。
ブランチオーガニックマーケットでの出店もみやぎ・なめとこ山の会の大切な活動の一つ。興味を持った人がいれば、まずは話を聞いてほしい。クマのニュースを見たとき、少しだけ視点を変えて考えてみてほしい——そんな思いで、今日も活動を続けている。
「まずは関心を持っていただければ」と小松さんは語る。年会費1,000円の応援会員から、活動に参加することができる。3.5%の人が動けば、状況は変わる。その一人に、あなたもなってみませんか。
つながる・みつけるポイント
みやぎ・なめとこ山の会では、以下のような方々とのつながりを求めています。
自然環境や生物多様性の保全に関心のある方、森林保全や水源保護に取り組む団体、そして環境教育に携わる教育関係者の方におすすめです。
また、「30by30」や「ネイチャーポジティブ」などの国際的な環境戦略に興味のある方、野生動物との共生や広葉樹の植樹活動に関心のある方、未来世代のためにできることを一緒に考えたい方にもぜひご参加いただきたい内容です。
講演会やイベントの企画・運営に協力いただける方も歓迎します。
また、仙台市環境局をはじめとする行政機関との連携も視野に入れています。「まずは話を聞いてみたい」という方も大歓迎です。小さな一歩から、一緒に未来を考えていきましょう。
日本熊森協会宮城県支部(みやぎ・なめとこ山の会)
会員募集中:年会費1,000円〜
詳しくは日本熊森協会のホームページをご覧ください。
日本熊森協会宮城県支部 連絡先 メール:km60011284jk@outlook.com
電話:090-9536-0887
作成・嶺岸ほのか
地域のみんなが主役。住宅エリアのまちづくりに
あなたも
寄付で参加しませんか?
まちスポ仙台は、仙台北部エリアを中心とした住宅地エリアが「選ばれるUPタウン」でありつづけるために、地域のみんなの想いや活動を日々後押しして支えています。まちスポ仙台への寄付で、ワクワクする地域を一緒につくりませんか?